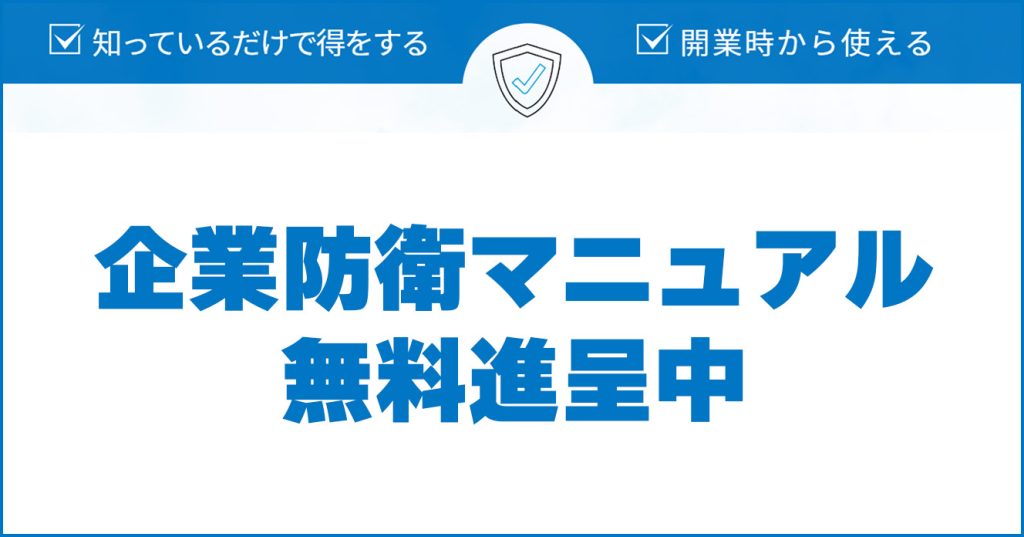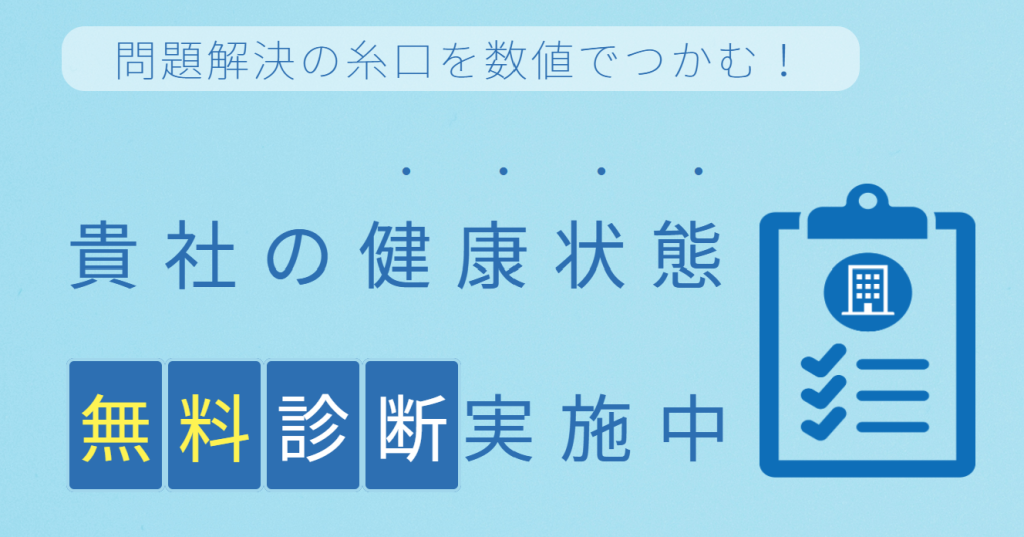今回は、弊社オリジナルの連載特集【過年度遡及修正会計基準の解説】第5回目をお届けいたします。
過年度遡及修正会計基準(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)を含む、各種決算業務でお困りの方
過年度遡及修正会計基準(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)など、会計処理の方法を手軽に聞きたいという方
この連載は、過年度遡及修正会計基準の解説を行うことを目的としたものですが、今回は、誤謬(過去の財務諸表に誤りがあった場合)の取り扱いについて解説したいと思います。
1.はじめに
誤謬は財務諸表の誤りのことであり、会計方針の変更などとは異なり、本来は生じてはならない性質のものです。「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)」(以下、「過年度遡及修正会計基準」)において、取扱いについては厳しく規定されています。
2.誤謬について
① 誤謬とは
誤謬について、「過年度遡及修正会計基準」においては、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいうとされています(過年度遡及修正会計基準4項)。
- 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
- 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
- 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り
誤謬については、意図的ではないものの、会計処理を誤った誤謬と、意図的に行われる不正による虚偽表示の、大きく分けて2つが存在しますが、「過年度遡及修正会計基準」においては、意図的であるか否かに関わらず誤謬として取り扱われます。
また、複数の会計処理の選択適用が認められる会計事象について、ある会計処理を選択適用したものの、その後の監査等において、会計処理が不適切であるとされ、別の会計処理に変更する場合も、一般的に誤謬として取り扱われることになります。
財務諸表の公表前に発覚した誤謬については修正を行えば、対外的には大きな問題は生じませんが、公表後に誤謬が発覚した場合は「過年度遡及修正会計基準」に基づき、処理を行うことが求められます。
② 誤謬が生じた場合の対応
過去の財務諸表における過去の誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示を行うことが求められます(過年度遡及修正会計基準21項)。
- 表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
- 表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
「最も古い期間」について、「遡及適用基準」では具体的な期間は定められていませんが、有価証券報告書においては、注記等を含めた全ての財務諸表については、当期と前期の2年間分のみが開示されますが、表紙の後に過去5年間の主な財務数値等が要約で記載されています。
このため、遡及適用も過去5年間分を遡って行うことが求められます。上場企業等では、現在、3か月ごとに四半期報告書において、財務諸表を開示することが求められているため、実際には最大で過去5年間の計20回分の財務諸表を遡及修正することになります。
また、過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、次の事項を併せて注記することが求められます(過年度遡及修正会計基準22項)。
- 過去の誤謬の内容
- 表示期間のうち過去の期間について、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額
- 表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映された、表示期間より前の期間に関する修正再表示の累積的影響額。
なお、その後に発行される財務諸表においては当該注記を繰り返す必要はありません(過年度遡及修正会計基準68項)。
会計上の変更では、会計方針の変更、表示方法の変更及び会計上の見積りの変更のそれぞれについて、取扱いが定められていますが、誤謬の場合はいずれも同じ処理方法となります。ただし、例えば、過去の時点から企業を取り巻く状況等が大きく変わったために、会計方針を変更する場合や、会計上の見積りにおいて、過去の財務諸表作成時には、その時点で入手可能な情報に基づき最善の見積りを行った場合等は、誤謬には当たらないため、修正再表示の必要はありません。
③ 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合
過去の情報が企業等で保存されていない場合や、遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合、遡及適用において会計上の見積りを必要とするときに、会計事象や取引が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合等には、遡及適用が実務上不可能な場合とされます(過年度遡及修正会計基準8項)。
この場合、実行可能な最も古い期間から遡及適用を行うことになります。
④ 内部統制への影響
誤謬が生じた場合、内部統制上も内部統制に欠陥等が生じていないかを検証する必要が生じます。その結果、誤謬が生じたことが、内部統制上、開示すべき重要な不備と判断された場合には、内部統制報告書上においても、当該誤謬について言及されることになります。
特に不正による誤謬が発見された場合には、内部統制上もより慎重な取扱いが求められます。
3.誤謬が起こらないよう、日常的に行うべき対応
過去の誤謬が発見されるのは、「決算時」であることが多いため、現在の決算を行いつつ、過去の決算についても修正を同時並行で行うことになり、多大な労力を要することになります(本当に大変です)。誤謬が生じないように、通常業務においても誤りが生じないような内部体制(仕訳の二重チェックなども含む)の構築を行うとともに、会計方針や会計上の見積り等について判断を行う場合は、事前に監査法人や会計コンサルタント等に確認することが、誤謬となる可能性を減らすのに有効となります。
過年度訴求修正会計基準連載
第1回目:過年度遡及修正会計基準の概要
第2回目:会計方針の変更があった場合の取扱い
第3回目:表示方向の変更があった場合の取扱い
第5回目:誤謬のがあった場合の取扱い(今回)
第6回目:過年度遡及修正の開示
◆関連事務所提供サービス◆
【オリジナルレポート】






過年度遡及修正会計基準(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)を含む、各種決算業務でお困りの方
過年度遡及修正会計基準(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)など、会計処理の方法を手軽に聞きたいという方